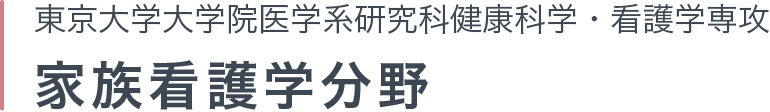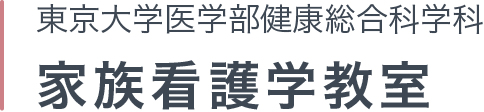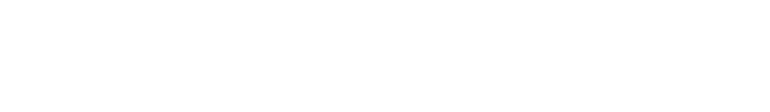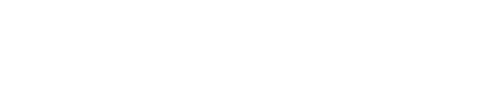- トップ >
- 大学院受験をお考えの方へ >
- 先輩からのメッセージ
卒業生からのメッセージ

中嶋 祥平
- 卒業年度
- 2018年度卒
- 現在の所属
- 東京大学医学部附属病院 小児科病棟(執筆時)
大学院では造血幹細胞移植を受ける患者と家族を対象とした研究を行いました。現在は移植後フォローアップ外来の研究を行いつつ、日々の業務の中で、論文などのエビデンスに基づいた看護を実践できるように心がけています。大学院で学習してからの臨床での業務は大変なことも多いですが、家族に対するケアを意識することができ、改めて進学してよかったと考えています。
当時の教室の同期は僕を含め7人で、今でもオンラインで交流しています。他愛のないことから現在の仕事や研究、今後のキャリアなどについて話し合うことができる、かけがえのない仲間を見つけることができました。
家族看護学教室では、さまざまな発達課題をもつ家族を対象とした研究について考えることができます。小児、母性、老年など多分野の研究に触れることができますし、研究の環境は非常に整っており、多様な研究方法を学ぶことができます。GNRCのセミナーなどで海外の著名な先生方の講義を聴くことができ、学会発表や論文執筆などの指導も行っていただきました。
教室の先生方はとても優しく、そして熱意ある指導を行っていただけると思います。ぜひ一度ご連絡してみてはいかがでしょうか。
鈴木 征吾
- 卒業年度
- 2018年度卒
- 現在の所属
- 東京医科大学医学部看護学科(執筆時)
私は小児病棟の看護師として在宅移行を支援する過程で、日常的に吸引や経管栄養などの医療を要する子ども(医療的ケア児)とその家族への看護支援に関心を持ち、家族全体を看護の対象として捉えた研究に必要な考え方や方法論を学びたいと考えて、家族看護学分野への進学を目指しました。
家族看護学分野のゼミでは、様々な領域の臨床経験や研究経験を持つ教室員とお互いの研究について率直に意見交換することで、毎回新たな気づきを得ることができました。同時期に在籍した大学院生の研究対象者は、成人がん患者の家族や家族を亡くした人など、医療機関内でのアプローチが容易でない場合や心理的負担への配慮が極めて重要な場合など状況も様々で、社会の中で光の当たっていない声を丁寧に集めることの大切さも学びました。
在籍中には、家族ケア症例研究会での事例発表とその論文化、医療的ケア児の保護者への健康関連QOL評価尺度による全国調査、および東大病院小児科外来における成人医療への移行支援に関する介入研究などを経験することができました。現在私は大学教員として、医療的ケア児の成人医療への移行に焦点を当てて、その家族へのケアも含めた研究を行っています。これは家族看護学分野と東大病院スタッフとの合同研究チームの一員として関わった成人医療への移行支援の経験と、臨床で抱いた疑問から博士課程を通じて取り組んできたテーマが結びついて発展した研究課題です。
進学をお考えの皆さんにとって、家族看護学分野で学ぶことは、家族というキーワードで結びついた多様な研究に囲まれて、多くの当事者とその家族の実体験に触れ、患者・家族中心とは何かを繰り返し考えながら、臨床実践に貢献する看護研究を遂行するための視座を広げる貴重な経験になることと思います。

松原 由季
- 卒業年度
- 2014年度(修士)/2010年度(学部)
- 現在の所属
- 公益社団法人日本看護協会 看護研修学校 教育研究部
私と家族看護との出会いは、大学の講義でした。理論に触れ、家族をシステムとして捉えアプローチする、という考え方が興味深かったことを覚えています。実習も進み、医療と生活の両面から患者を捉える必要性を実感していた中で、その面白さを感じ、家族看護学分野を選択しました。実際に、卒後看護師として勤務する中で、適切なケアや意思決定には家族看護が必要であり、看護だからこそ提供できる家族も含めたケアの可能性を感じました。そして、看護提供の基盤となる、エビデンスや制度・仕組みに関わっていきたいと思い、家族看護学分野の修士課程に進学しました。
教室には様々な研究テーマを持った先生や先輩・後輩がいました(それこそ妊産婦から臨死期も)。皆「家族」に関心があり、対象とする家族の形はそれぞれで、様々な測定や分析方法を検討していました。そのため、私の研究テーマは小児でしたが、カンファレンスでの研究発表後には「どのようにしたら今回知りたいことを捉えることができるか」と熱く意見を交わすこともあり、得難い経験だったと印象に残っています。
現在の仕事では、情報の収集や分析をして、臨床現場や様々な場の方からご意見を伺いながら、どうあるべきかを考える、ということをしています。大学院で培った論理的思考や、様々な視点から検討して真実を探求する、という経験が活きていると感じています。
進学のきっかけは、気づき、疑問、問題意識、心残りなど、何でもいいと思います。ライフサイクルのどの段階に関心がある人も、「家族」の事象を捉える多様な経験のある先生方とともに、知的探求心をもって研究の世界に飛び込んでみてはいかがでしょうか。
大学院生からのメッセージ
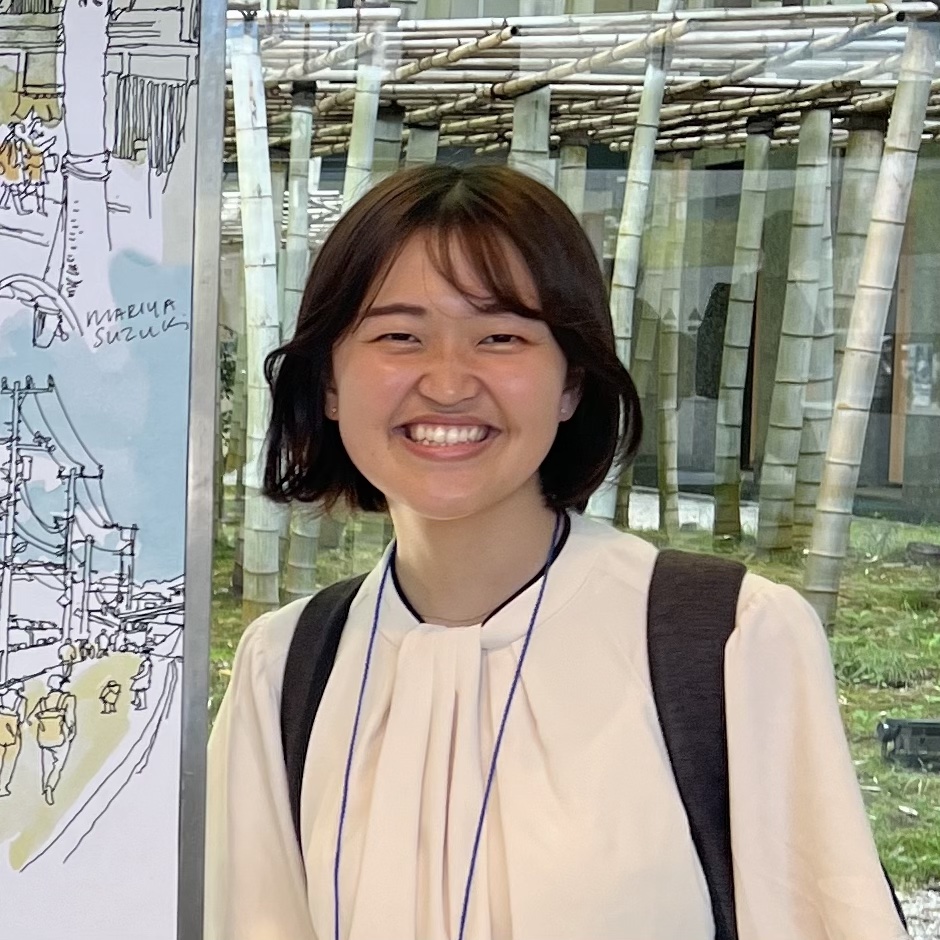
下山 結衣(修士課程)
私は学部生の頃に、卒論生として家族看護学教室でご指導いただきました。先生方は私の興味や関心を受け止め、多くのサポートをしてくださったこと、大変ありがたく思っています。自分の関心分野に踏み込んでいると感じてワクワクしながらも、初めての経験で困難に直面することもありました。それを乗り越えられたのは、教室員のみなさんに精神的にも支えられていたからだと思います。やりたいことを尊重し、頑張ることを応援してくれる、そんな環境がとても居心地良く、大学院に進学してさらに頑張ることを決意しました。大学院では、目の前のことに精一杯の日々ではありますが、非常に充実した日々を送っています。一緒に取り組む仲間、日頃の頑張りをねぎらい合える仲間として、みなさんにお会いできる日を楽しみにしています。

堀 静穂(修士課程)
私は、小児集中治療室や児童精神科にて看護師として従事し、公認心理師としての資格を取得しました。発達の特性や生きづらさを抱える子どもとその家族に対する支援の在り方に論点を持ち、大学院に進学しました。現在は、子どものメンタルヘルス、とくに思春期の「社会的カモフラージュ行動」に焦点を当てた研究を行っています。この教室は、いつでも温かく、家族のように私を支えてくれ、研究の壁に直面しても、寄り添いながら共に進んでくれるかけがえのない居場所です。もし「家族看護」に関する研究に興味があれば、この教室で新たな視点が見えてくるかもしれません。一緒に学べる日を心から楽しみにしています。

加藤 真希(修士課程)
私は、大学院入学前に15年ほど行政保健師として勤務しており、地域の母子保健・精神保健業務に従事しておりました。大学院入学のきっかけになったのは、自身が乳がんに罹患したことでした。これからの自分の人生を立ち止まって考え、どのように社会に貢献していくかを考える機会となりました。次世代を担う子ども達とその家族にとって、少しでもよりよい社会であってほしい、そのために自分は何が出来るのかを日々考えながら、勉強・研究に取り組んでいます。家族看護学教室では、素晴らしい先生方と志の高い先輩・仲間に恵まれ、子育てに追われながら学ぶ私を日々励まして下さりながら、手厚くご指導下さり、この上ない学習環境に日々感謝しています。私自身、まだまだ勉強不足なことばかりですが、たくさんの仲間と新たに出会い、共に学べることを楽しみにしております。

新居田 佳祐(修士課程)
私は大学院進学前、NICU・小児科で勤務し、そこで退院支援した子どもを乳児院に繋いだ経験から、ケアを必要としているのは病院の子どもだけではないと気づきました。自身も乳児院で勤め、その後大学に編入学し社会福祉士の資格を取得後こちらの大学院に進みました。家族看護学教室では、私のように子どもの領域に関心のある方から、成人、周産期など多様な研究テーマを持った学生、先生方が在籍しています。学部からさらに学びを深めたい方、臨床経験を経て課題意識を持っている方、様々な志願者がいらっしゃると思いますが、先生方の手厚いご指導の下とても充実した院生生活が送れると思います。ぜひ一緒に学びましょう。

秋山 美咲(修士課程)
私はこれまで、産科・NICUで助産師として従事してきました。ご家族の一生に携わる助産師として、母子だけでなくご家族全体に寄り添うケアを追求したいと思い進学しました。この教室では、様々な経歴や研究テーマを持つ先生方や仲間がおり、自分の関心以上に学びが広がることを実感する日々を送っております。家族看護に興味のある方には非常に充実した学びの場です。新たな仲間と一緒に学べる日を楽しみにしています。